企業ホームページ運営のコツは「訪問者は自社を知らない」と自覚すること
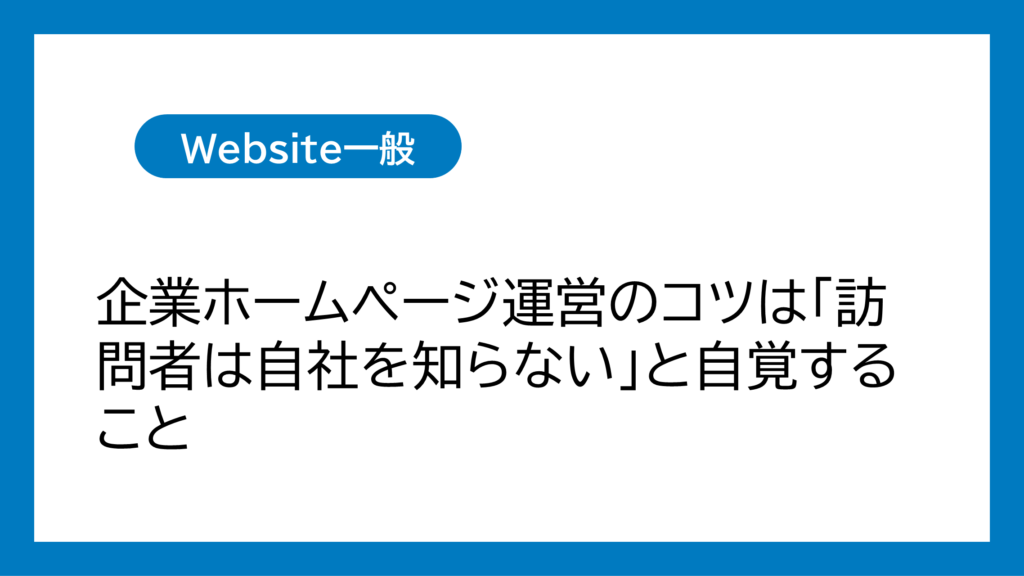
はじめに
皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?「せっかくホームページを作ったのに、なかなかアクセス数が伸びない…」「問い合わせも少ないし、効果が出ているのかわからない…」
実は、多くの企業が陥りがちな落とし穴があるんです。それは「訪問者は自社のことをよく知っている」という思い込み。でも、実際はそうじゃないんです。今日は、この視点を変えるだけで、ホームページの効果を劇的に高められる方法をお伝えします。
この記事を読めば、訪問者の目線に立ったホームページ作りのコツがわかり、小規模企業でも大手に負けない魅力的なサイトを作れるようになります。それでは早速見ていきましょう。
1. 「自社を知らない」という前提で考えることの重要性
1-1. 潜在顧客の視点に立つ:自社のことよりも、顧客が何を求めているのか
まず大切なのは、ホームページを訪れる人の立場になって考えること。彼らは自社のことを全く知らないかもしれません。そんな人たちに、どうすれば自社の魅力を伝えられるでしょうか?
例えば、「弊社は創業50年の歴史ある会社です」という情報。確かに素晴らしいことですが、初めて訪れた人にとっては「だから何?」となりかねません。代わりに「50年間で培った技術で、お客様の悩みを素早く解決します」とすれば、訪問者にとってのメリットが明確になりますよね。
つまり、自社の歴史や規模よりも、「お客様にとってどんな価値があるのか」を考えることが大切なんです。これが、潜在顧客の心をつかむ第一歩となります。
1-2. 小さな会社だからこそできること:大企業との差別化戦略
「うちは小さな会社だから…」と思っていませんか?でも、それこそが強みになるんです!大企業にはできない、小規模企業ならではの魅力をアピールしましょう。
例えば、「社長が直接対応します」「お客様一人一人に合わせたカスタマイズが可能」といった点は、大企業では難しいサービスです。また、地域に密着した活動や、フットワークの軽さも小規模企業の強みです。「地元の○○商店街の活性化プロジェクトに参加しています」といった情報は、地域の人々との繋がりを感じさせ、親近感を生みます。
小規模だからこそできる、きめ細やかなサービスや地域との密接な関係性。これらを前面に出すことで、大企業との差別化を図れるんです。自社の規模を恥じる必要はありません。むしろ、それを強みに変えていきましょう!
2. ホームページで伝えたいことを明確にする
2-1. 競合との違いを際立たせる:強みと特徴を絞り込む
ホームページを作る上で重要なのは、自社の強みを明確にすること。でも、「うちの会社って何が強みなんだろう?」と悩む方も多いはず。そんな時は、競合他社と比較してみるのがおすすめです。
具体的には、以下のステップで考えてみましょう: 1. 競合他社のホームページを5つほど見てみる 2. それぞれの特徴や強みをメモする 3. 自社にしかない特徴や、自社の方が優れている点を探す
例えば、同じ製品を扱っていても、自社は「24時間対応のカスタマーサポート」があるかもしれません。または「環境に配慮した製造過程」が特徴かもしれません。これらの点を強調することで、競合他社との違いが明確になり、選ばれる理由を作ることができるんです。ポイントは商品、サービスと直接対決しない内容を探すことです。
ただし、あれもこれもと欲張りすぎないことが大切。「うちは何でもできます!」というメッセージは、幅広くできて良いように思いがちですが、実は逆に印象が薄くなってしまいます。2〜3つの強みに絞り、それを徹底的にアピールすることをおすすめします。
2-2. ターゲット顧客に響く言葉を選ぶ:ペルソナ設定の重要性
次に大切なのは、誰に向けて語りかけるかを明確にすること。これを「ペルソナ設定」と呼びます。少し難しく聞こえるかもしれませんが、要は「理想的なお客様像」を具体的にイメージすることです。
例えば、「2人の子供がいいるために時間に追われている30代後半の共働き夫婦。健康には気を使いたいが、忙しくて手が回らない」といった具合です。このように「xxxが原因でxxxの課題を抱えているxxxの属性の方」をペルソナとして、その方に向けて語りかけるように文章を作ると、より響く言葉が見つかります。このカッコ内はもちろん商品、サービスについて当てはまるものです。
「忙しい毎日でも、簡単に栄養バランスの取れた食事を」「子育て世代の悩みに寄り添います」といった言葉は、まさにこのペルソナに刺さるメッセージになりますよね。
「でも、お客様は一人じゃないのに…」と思うかもしれません。確かにその通りです。しかし、特定の人物像に向けて語りかけることで、メッセージの具体性が増し、結果的により多くの人に響くことが多いんです。ぜひ、自社の理想的なお客様像を描いてみてください。
3. 分かりやすく魅力的なコンテンツ作り
3-1. 自社の強みを簡潔に伝えるメッセージ作成
ホームページを訪れた人が最初に目にするのは、多くの場合トップページです。ここで、自社の強みを簡潔に、でも印象的に伝えることが重要です。これを「キャッチコピー」や「キャッチフレーズ」と呼びます。
良いキャッチコピーの特徴は以下の通りです:
- 1. 短くて覚えやすい(15文字程度が目安)
- 2. 自社の強みや特徴が端的に表現されている
- 3. 顧客にとってのメリットが明確
- 4. 独自性がある(他社と差別化できる)
例えば、「毎日の食卓に、安心と笑顔を」というキャッチコピーがあったとします。これは食品会社の場合、安全性(安心)と家族の幸せ(笑顔)という価値を簡潔に表現しています。
キャッチコピーを考えるのは少し難しく感じるかもしれません。そんな時は、まず自社の強みや顧客へのメリットを箇条書きにしてみましょう。その中から特に伝えたいことを選び、それを短い文章に凝縮していくのです。完璧を求めすぎず、何度も試行錯誤することが大切です。
3-2. 視覚的に訴求するデザインとレイアウト
文章だけでなく、視覚的な要素も重要です。ここでは、専門的なデザインスキルがなくてもできる、基本的なポイントをお伝えします。
- 1. 色使い:3色程度に抑える
企業カラーを中心に、2〜3色程度で統一感を出します。多色使いは避けましょう。 - 2. 余白を大切に
情報を詰め込みすぎず、適度な余白を設けることで見やすさが格段に向上します。 - 3. 画像の活用
製品やサービスの写真、スタッフの笑顔など、適切な画像は千の言葉よりも雄弁です。 - 4. フォントは2種類まで
見出しと本文で異なるフォントを使用する程度に抑えましょう。
「でも、デザインは苦手で…」という方も多いはずです。その場合は、無料のテンプレートを活用するのも一案です。WordPressなどのCMSを使用すれば、ある程度見栄えの良いデザインを簡単に適用できます。
ただし、完璧を求めすぎないことが大切です。内容の充実を優先し、デザインは徐々に改善していく姿勢で構いません。「見た目は今一つだけど、内容が素晴らしい」というサイトの方が、「見た目は華やかだけど、中身が薄い」サイトよりもずっと価値があります。
4. 信頼を築くための基本的な要素
4-1. 実績や顧客の声を効果的に掲載する方法
お客様に選んでいただくためには、信頼感の醸成が欠かせません。そのための有効な方法が、実績や顧客の声の掲載です。ただし、ただ羅列するだけでは効果は半減します。効果的な掲載方法を見ていきましょう。
実績の掲載:
- 数字を使う:「顧客満足度98%」「リピート率80%」など
- 具体的な事例を挙げる:「A社の売上が前年比120%に向上」
- 経年変化を示す:グラフなどを使って成長の様子を可視化
顧客の声:
- 具体的なメリットを含める:「導入後、作業時間が30%削減されました」
- 写真や動画を活用:可能であれば、実際のお客様の顔写真や動画メッセージ
- 多様性を意識:様々な業種、規模の顧客からの声を掲載
ここで注意したいのは、あまりに誇張した表現や、疑わしい数字は逆効果だということ。「世界No.1」「100%の満足度」といった表現は、ユーザーは疑った気持から見てしまいます。謙虚さを保ちつつ、着実な成果を示すことが大切です。
また、個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。顧客の声を掲載する際は、必ず本人の許可を得ること。可能であれば、掲載前に内容の確認もしてもらうのがベストです。
4-2. プロフェッショナルなイメージを演出する工夫
小規模企業だからこそ、プロフェッショナルなイメージづくりが重要です。ここでは、専門知識や高額な投資なしでもできる工夫をご紹介します。
1. 正確な情報提供:
• 誤字脱字のチェックを徹底する
• 定期的に情報を更新し、古い内容を放置しない
• 参考文献や出典を明記する
2. レスポンシブデザインの採用:
• スマートフォンでも見やすいサイト設計にする
• 表示速度の改善(大きすぎる画像の圧縮など)
3. セキュリティへの配慮:
• SSL証明書の導入(https化)
• プライバシーポリシーの明記
4. 分かりやすい問い合わせ方法:
• 問い合わせフォームの設置
• 電話番号やメールアドレスの明記
• SNSアカウントとの連携
「レスポンシブデザイン」や「SSL証明書」といった言葉に戸惑う方もいるかもしれません。少し専門的になりますが、これらは実はとても重要な要素なんです。分からない部分があれば、ウェブ制作会社に相談するのも一案です。ただし、自分でも基本的な知識を持っておくことで、外注する際にも適切な判断ができるようになります。
プロフェッショナルなイメージは、一朝一夕には作れません。しかし、これらの基本的な要素を少しずつ取り入れていくことで、着実に信頼性を高めていけるのです。焦らず、一つずつ改善していく姿勢が大切です。
5. 小規模ビジネスならではの親近感の演出
5-1. 社長やスタッフの紹介で親しみやすさをアピール
小規模企業の強みの一つは、「顔が見える」ということ。これを最大限に活かしましょう。社長やスタッフの紹介ページを作ることで、親しみやすさと信頼感を演出できます。
効果的な紹介方法:
- 笑顔の写真を掲載
- 経歴だけでなく、趣味や好きな食べ物など、人となりが分かる情報も
- 仕事に対する想いや、お客様へのメッセージを記載
- 動画メッセージを掲載(可能であれば)
例えば、「休日は娘とキャンプに行くのが楽しみです」といった一言があるだけで、親近感がぐっと増しますよね。ただし、プライバシーに配慮することも忘れずに。掲載する情報は、スタッフ一人一人の同意を得ることが大切です。
「でも、うちはまだ一人で やっているんです...」という方もいるかもしれません。その場合でも大丈夫です。むしろ、「一人で全力投球しています!」といったメッセージは、誠実さや熱意を感じさせ、好印象を与えることができます。
5-2. 地域に根ざした活動や取り組みの紹介
小規模企業の強みの一つは、地域との密接なつながり。この強みを活かすために、地域に根ざした活動や取り組みを積極的に紹介しましょう。
紹介できる活動例:
- 地域のお祭りやイベントへの参加
- 地元の学校での講演や職業体験の受け入れ
- 地域の清掃活動やボランティア活動
- 地元の他企業とのコラボレーション
これらの活動を紹介することで、「この会社は地域のことを大切にしている」という印象を与えることができます。また、活動の様子を写真や動画で紹介すれば、より具体的に伝わります。
ただし、こういった活動は「アピールのため」だけに行うのではなく、真に地域に貢献したいという思いが大切です。その思いが伝わってこそ、本当の信頼関係が築けるのです。
6. 具体的な行動に繋がるホームページ設計
6-1. 見やすいデザインと分かりやすい情報配置
ホームページの目的は、最終的に具体的な行動(問い合わせや購入など)に繋げることです。そのためには、ユーザーが欲しい情報にスムーズにたどり着けるデザインと構造が必要です。
ポイント:
- メニューは分かりやすく整理する(5〜7項目程度が理想)
- スクロールせずに重要な情報が見えるようにする
- 読みやすいフォントとサイズを使用する
- コントラストを意識し、背景と文字の色を適切に選ぶ
- スマートフォンでも見やすいレスポンシブデザインを採用する
例えば、「サービス」「料金」「お問い合わせ」といった重要な情報へのリンクは、どのページからもアクセスしやすい位置に配置しましょう。また、長文は適度に段落分けし、見出しをつけることで読みやすくなります。
「でも、デザインって難しそう...」と思う方もいるかもしれません。確かに、プロのデザイナーほどの技術は必要ありません。むしろ、シンプルで機能的なデザインの方が、情報が伝わりやすいことも多いんです。無料のテンプレートを活用し、そこから少しずつカスタマイズしていく方法もおすすめです。
6-2. お問い合わせや資料請求に繋がりやすい仕組み作り
最後に、訪問者の行動を促す仕組み作りについて考えましょう。これは「コンバージョン(CV)」と呼ばれる重要な要素です。
効果的な方法:
- 分かりやすい位置に「お問い合わせ」ボタンを配置
- フォームの入力項目は必要最小限に抑える
- 「資料請求」や「無料相談」など、気軽に利用できるサービスを用意
- 電話番号やメールアドレスを明記(特に問い合わせページ以外でも)
- SNSアカウントへのリンクを設置
例えば、「まずは資料請求から」というボタンを目立つ位置に配置することで、顧客の行動を促すことができます。また、問い合わせフォームは、名前とメールアドレスなど最低限の情報だけを聞くようにし、ハードルを下げるのも効果的です。
ただし、やや専門的になりますが、過度に押し付けがましい表現(例:点滅する「今すぐ申し込め!」ボタンなど)は、逆効果になる可能性があります。ユーザーの立場に立って、自然に次の行動に移れるよう工夫してください。
まとめ
この記事では「訪問者は自社を知らない」という視点に立つことで、ホームページの見え方が大きく変わってくることについて例を挙げながら説明してきました。ここで紹介した方法を一つずつ実践していくことで、より効果的なホームページを作ることができます。
ただし、これらの改善はやればすぐに大きな成果になるというわけではありません。少しずつ、できることから始めていきましょう。そして、定期的にアクセス解析ツールなどを使って効果を検証し、さらなる改善につなげていくことが大切です。
最後に、どうしても自力での対応が難しい場合は、ウェブ制作の専門家に相談するのも一案です。ただし、その場合でも、この記事で学んだ基本的な考え方を理解しておくことで、より良い相談や依頼ができるはずです。
この記事を読んで、さらに深掘りしたい点がございましたら、ぜひWebrickにお声がけください。代表の安藤がていねいにお答えいたします。
mwform_formkey key=”1672″]
